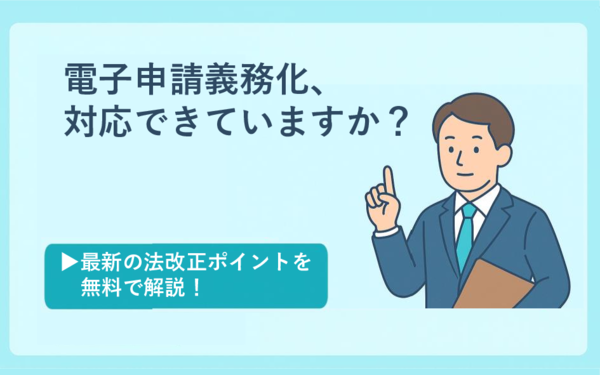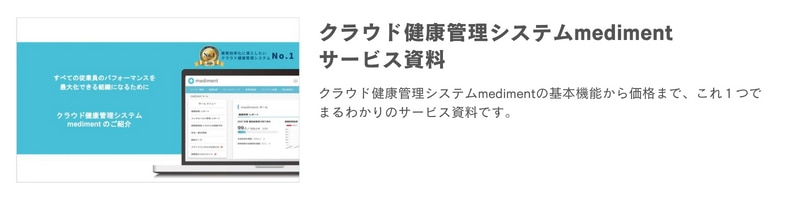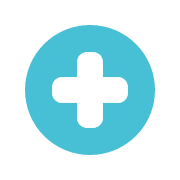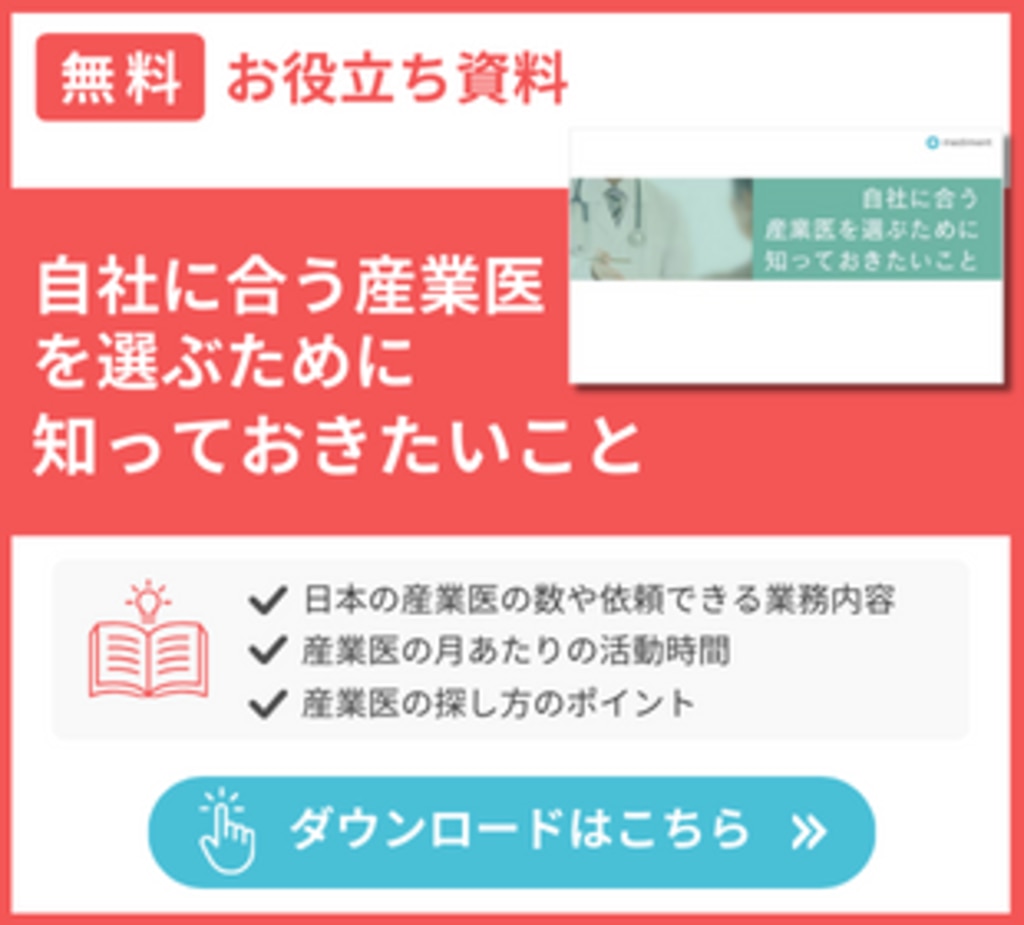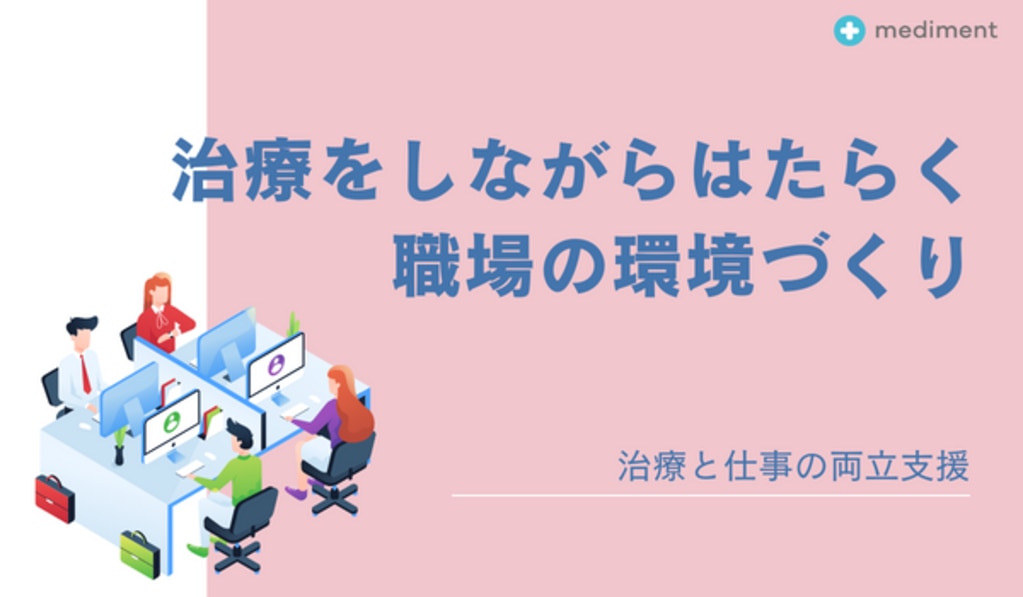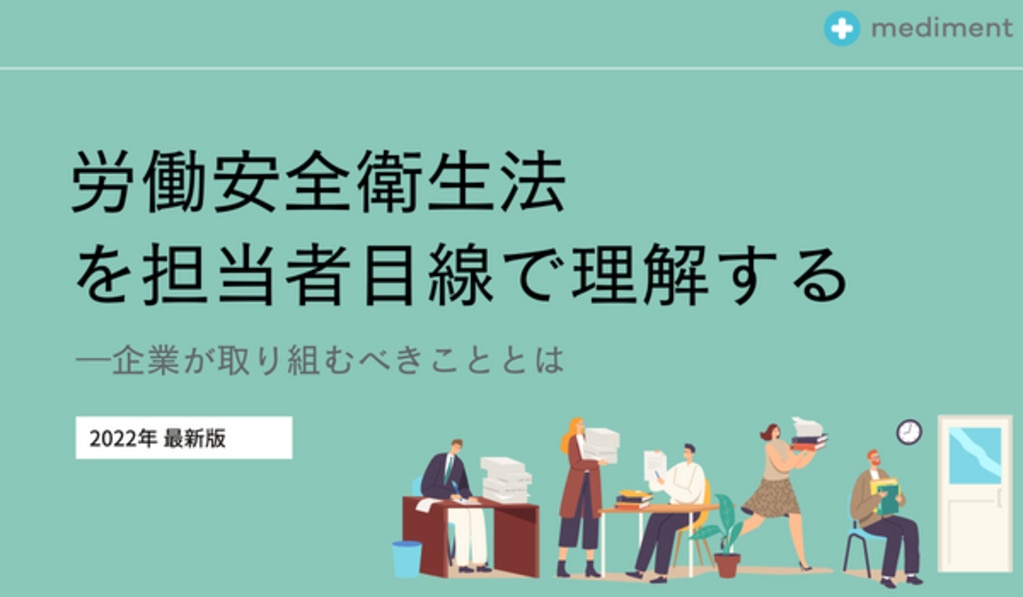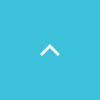産業医面談とは?対象基準や実施方法、企業が押さえるべきポイント
企業において従業員の健康管理は重要な課題の一つです。特に長時間労働やストレスによる健康リスクが高まる中、産業医面談は従業員の健康を維持し、職場環境の改善を図るための有効な手段とされています。本記事では、産業医面談の目的や実施基準、企業が押さえるべきポイントについて詳しく解説します。
目次[非表示]
以下の資料は、電子申請義務化の背景と、企業が取るべき具体的な対応策をまとめた資料です。ぜひ業務にお役立てください。
>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :電子申請義務化の背景と対応策を解説
>>>産業医についてはこちらの記事をチェック
産業医面談とは?目的や企業と産業医の義務
まずは産業医面談とは何なのか、目的や企業と産業医、それぞれの義務について見ていきます。
産業医面談の目的と役割
産業医面談は、従業員が健康的に働くために実施される重要な制度です。特に、メンタルヘルスや身体の不調を早期発見し、適切な対策を講じることを目的としています。
産業医は中立的な立場で従業員の健康相談に応じ、企業へ職場環境の改善を助言する役割を担っています。
企業と産業医の関係
企業は産業医と連携し、従業員の健康管理を行う義務があります。人事担当者は、必要に応じて適切なフォローアップを行うことが求められます。産業医の主な業務として、以下が挙げられます。
・従業員の健康相談とメンタルサポート
・職場環境の改善指導
・健康診断結果の確認と就業可否の判断
企業が産業医面談を実施する義務とは
企業には「産業医の選任義務」があります。(労働安全衛生法第13条)。
また、長時間労働者や高ストレス者への面談は「実施義務」となっており、労働安全衛生法第66条に基づき適切に対応することが求められます。
【参考】 「労働安全衛生法」 (e-Gov 法令検索)
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
産業医の義務とは
産業医には、主に以下の2つの義務があります。
・守秘義務:従業員の健康情報を適切に管理し、第三者に漏洩しないこと。
・報告義務:企業に対して従業員の健康状態に関する助言や指導を行うこと。
また、産業医だけでなく、保健師が従業員の相談窓口としてサポートを行うケースもあります。社内で適切な健康管理体制を整えることで、従業員が安心して働ける環境を構築することができます。
従業員が心身共に健康的に働けるように、産業医は企業と従業員の中立的な立場で企業へ報告をおこないます。 ただし、報告義務より守秘義務が優先されるため、企業側に報告する際は従業員の同意が必要です。 守秘義務については、刑法に定められており、産業医も該当します。
刑法第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
また、労働安全衛生法105条にも守秘義務について定めがあります。
労働安全衛生法105条 (健康診断等に関する秘密の保持) 第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。引用:労働安全衛生法 労働安全衛生法 | e-Gov法令検索
以下の資料は、電子申請義務化の背景と、企業が取るべき具体的な対応策をまとめた資料です。ぜひ業務にお役立てください。
>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :電子申請義務化の背景と対応策を解説
産業医面談のメリットとは?企業と従業員双方の利点
産業医面談は、企業と従業員双方に多くのメリットをもたらします。早期の健康リスク発見、企業リスクの軽減、生産性向上など、企業側の利点に加え、従業員も心身の健康相談や労働環境改善の機会を得られます。両社のメリットについて詳しく解説します。
企業側のメリット
メンタルヘルス不調や健康リスクの早期発見
産業医面談を通じて、ストレスや体調不良を抱えた従業員を早期に発見できます。これにより、早めに対策を打つことで、長期休職や離職を防ぎ、企業全体の生産性を維持することが可能です。
健康問題による企業リスクの軽減
健康管理が不十分だと、労災事故や法的問題が発生するリスクが高まります。産業医面談を実施することで企業の法的責任を果たし、リスクを未然に防ぐことができます。特に、情報通信機器を活用したテレワーク環境においても、適切な健康管理が求められます。
生産性の向上
産業医面談を積極的に活用することで、企業文化として健康経営を推進できます。これにより、従業員の健康が守られるだけでなく、離職率の低下や採用力の強化にも期待できます。
従業員側のメリット
心身の不調を相談しやすくなる
産業医は中立的な立場で従業員の健康状態や職場環境について話を聞くため、従業員が気軽に相談できる環境が整います。特に、高度プロフェッショナル制度の対象者のように長時間労働が発生しやすい業務に従事する社員にとって、面談は重要な機会となります。
健康状態の改善につながる
産業医から生活習慣や体調管理について具体的なアドバイスを受けることで、従業員の健康維持が促進されます。また、健康診断の結果についても、適切なアドバイスを受けられます。
適切な労働環境を確保しやすくなる
産業医は企業に対して長時間労働の是正や業務負担の軽減を提案できるため、従業員が働きやすい職場環境の整備が期待できます。
キャリアや働き方の見直しができる
産業医面談を通じて、自身の働き方を見直すきっかけを得ることができ、必要に応じて配置転換や勤務形態の変更を相談することも可能です。特に、休職中や復職時の相談内容として重要視されるポイントの一つです。
産業医面談の対象基準5つ|誰が面談を受けるべきか
産業医面談の対象者基準は、ストレスチェック結果、長時間労働、健康診断の結果、休職・復職・退職の希望、職場環境の問題などです。従業員の健康状態や状況に応じて、面談が必要かどうかを判断します。
①ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員
労働安全衛生法によるストレスチェックでは、50名以上の事業場は毎年1回ストレスチェックの実施が義務です。高ストレスと判定された従業員のうち、本人から申し出があった場合は、医師による面接指導が定められています。
ストレスチェックの高ストレス者とは、厚生労働省によると「自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周知のサポート状況が著しく悪いもの」と位置付けられています。
ストレスチェックについては、以下の記事で詳しく解説しています。
②長時間労働の従業員
労働安全衛生法により時間外・休日労働をしている従業員に対して、疲労の蓄積が認められた場合は産業医や医師による面接指導をすることが義務付けられています。
(面接指導等)
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
引用:労働安全衛生法 労働安全衛生法 | e-Gov法令検索
一定の残業時間の基準を超えた従業員には、毎月疲労蓄積度チェックリストというアンケートに回答してもらい、疲労の蓄積度合いを確認してハイリスク者には産業医面談を実施すると良いでしょう。
③健康診断の結果に気になる項目がある従業員
労働安全規則第14条第1項目第1号により、従業員の健康保持のために適切な措置を取るように義務付けられています。措置の一つとして挙げられるのが産業医面談による面接指導です。
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
健康診断受診後に、気になる項目があり、再検査や治療が必要だと結果が出たとしても、再検査をしない従業員もいます。医療機関を受診する前段階として産業医面談を実施したり、産業医面談で従業員に医療機関の受診を勧めたりするケースがあります。
④休職・復職・退職に関する相談を希望する従業員
休職・復職・退職などについては、企業の就業規則に則って実施されるケースが多いです。
休職者面談では対象者の心身の状態を確認し、休職の原因や主治医の診断書を元に意見書を作成し、企業へ提出します。休職の判断は産業医が下すのではなく、企業が産業医の意見を聴いて最終的に判断します。
休職者が復職を希望する際は主治医の診断書に加え、産業医面談をおこない、企業が復職可能か判断します。
また、退職について相談することも可能です。産業医が退職を引き留める、また退職勧告をすることはありませんが、退職したいと考える原因について聞き取り、対応を考えられます。
⑤職場環境の問題などで面談を希望する従業員
1〜4以外にも、従業員が産業医面談を希望した場合には産業医面談を実施します。また、企業が従業員に対して産業医面談を受けたほうがいいと判断し、勧めるケースもあります。面談の基準などは特に決められていません。
パワハラ・セクハラといった労働環境についての相談も可能です。
以下の資料は、電子申請義務化の背景と、企業が取るべき具体的な対応策をまとめた資料です。ぜひ業務にお役立てください。
>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :電子申請義務化の背景と対応策を解説
産業医面談の実務フロー|事前準備からアフターフォローまで
ここでは、産業医面談の実施に向けた事前準備から、実施後のフォローに至るまで、企業が実施するフローを解説します。
事前準備~面談の実施まで
産業医面談を円滑に進め、従業員の心身の健康を適切にサポートするためには、人事・労務担当者が事前準備から面談本番までの対応が大切です。
産業医面談に関わる実務をおこなう際には、プライバシーに充分に配慮しましょう。
1.面談の対象者を選定する
最初に、産業医面談の対象となる従業員を決定します。
労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックで高ストレス判定が出た従業員と長時間労働と判定された従業員に対し、本人が希望した場合には産業医面談をおこなう義務があります。
また、健康診断の結果、気になるところがある従業員から面談の希望があった場合にも産業医面談をおこないます。
2.面談の実施日時・場所の選定(対面・オンライン)
対象者を選定したら、面談の日時と面談の場所を決定します。対面の場合は面談内容が他の従業員に聞こえないよう配慮し、個室を確保しましょう。リモートワークや出向している従業員などはオンライン面談も可能です。
オンライン面談の場合は、対面の産業医面談と差が出ないようにしましょう。
3.従業員へ面談を案内する
産業医面談の日時・場所が決定したら、従業員へ面談の案内をします。周囲に産業医面談を受けることを知られないよう、封書やメールを用いたり、個人面談をしたりするなどして配慮してください。
また、オンライン面談の場合は、web会議システムを利用しての面談となります。産業医が面談相手の表情や顔色を確認できるよう、従業員には部屋の照明や周りの音を調整してもらうよう依頼しましょう。
4.産業医に事前情報を送る
産業医面談を実施する前の事前準備として、対象の従業員の健康情報や労働時間などを産業医に伝え、従業員の状況がわかるようにしておきます。
産業医に伝える情報は以下のとおりです。
- 従業員の健康診断結果
- 従業員・所属部署全体のストレスチェックの結果
- 従業員・所属部署全体の直近の残業時間
- 疲労蓄積度チェックリストの回答結果
- 過去に産業医面談の履歴がある場合は内容など
5.産業医面談を実施する
産業医面談は、産業医と従業員の1対1でおこなう場合が多いです。対面にておこなう場合は、産業医が会社に来社したらその日のスケジュールを確認し、会議室などに案内します。
面談を予約していた従業員に順番に来てもらい、スムーズに面談がおこなえるようサポートしましょう。
オンライン面談の場合は、web会議システムを使用しておこないますので、通信機器の設定などに問題がないかを事前に確認しておきましょう。
アフターフォロー
産業医面談は、実施したら終了というわけではなく、実施後のアフターフォローが大切です。
- 面談した記録と産業医からの意見書を適切に保管する
- 面談結果を元に企業としての対応を決める
以上2つのアフターフォローをおこないましょう。
1.面談した記録と産業医からの意見書を適切に保管する
産業医面談後は、面談の記録と意見書を5年間保管するよう定められています。(労働安全衛生規則第52条の6)
企業は、産業医面談の記録や意見書を適切に保管しましょう。記録や意見書は従業員のデリケートな問題を含む大切な個人情報ですので、保管する際には担当者以外が見れないように厳重に管理します。
第五十二条の六 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
2.面談結果を元に企業としての対応を決める
産業医面談後、面談記録や産業医の意見書をもとに、企業としてどのような措置を取るべきかの対応を決定します。
例えば、就業制限をかける場合には、どのような内容にすべきかなどを、産業医や該当の従業員の上司と連携しながら進めましょう。
対応を決める際には、該当の従業員のプライバシーに配慮し、不利益を被ることがないように注意しましょう。
産業医面談で話す内容とは
産業医面談では、メンタルヘルスや体調、生活習慣についての確認を行い、課題に対して適切な対策を講じることが求められます。今回は、産業医面談で話すべき主な内容をご紹介します。
産業医がよく聞く質問とは
①メンタルヘルス不調・ストレスチェック結果について
メンタルヘルス不調の原因は、職場内の人間関係や長時間労働、業務の内容などさまざまです。メンタルヘルスの問題は相談しにくいと感じる従業員も多いため、人事・労務担当者は、対象者が相談しやすいよう配慮しましょう。
メンタルヘルス不調に関する問題は進行が早いので、早期に発見し対処する必要があります。
*質問例
「最近ストレスを感じることはありますか?」
「職場の人間関係で困っていることはありませんか?」
②体調・健康診断結果について
【体調】
産業医面談では睡眠時間や食事はしっかりと取れているか、自覚症状がないかなど、体調についての質問をします。産業医は疾患を治療することはできませんが、医療機関を受診すべきかのアドバイスをします。
特に、健康診断で以下のような異常が見つかった場合には、体調について細かく確認し、従業員の健康管理をサポートします。
- コレステロール値が高い
- 高血圧
- 高血糖
- 肝臓の数値が高い
- 心電図異常
- 貧血
- 肥満
【健康診断の結果】
産業医は健康診断の結果に基づき、従業員本人の年齢や性別、生活習慣、就業状況などの情報から改善に向けてアドバイスや保健指導をおこないます。
企業は健康診断の実施後、所見がある従業員について3ヵ月以内に従業員の就業内容に問題がないか、医師による意見を受けなければならないと定められています。(労働安全衛生規則第51条の2)
第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
*質問例
「最近の健康状態に変化はありませんか?」
「睡眠時間や食事はしっかりと取れていますか?」
③生活習慣・就労状況について
【生活習慣】
産業医面談では、以下のような生活習慣について産業医から従業員へ聞き取りをします。
- 喫煙や飲酒の習慣はあるか/増加していないか
- 睡眠時間の増減はないか
- 生活リズムは規則正しいか
- 運動習慣は適切か
- 食事量・回数は適切か
【就労状況】
長時間労働などの就労状況について従業員に聞き取りをおこないます。長時間労働は疲労が蓄積するため、心臓や脳に影響を及ぼす危険性が高いです。
産業医は対象者の健康状態を把握し、健康障害の発症を予防するためのアドバイスをおこないます。
面談後、産業医は就業判定や必要な措置に関する意見書を作成し、企業は産業医の意見を踏まえ、就業状況改善をおこないます。
*質問例
「お酒やタバコの習慣はありますか?量は増加していませんか?」
「規則正しい生活を送れていますか?」
④休職・復職・退職に関する相談
【生活習慣】
産業医面談では、以下のような生活習慣について産業医から従業員へ聞き取りをします。
- 喫煙や飲酒の習慣はあるか/増加していないか
- 睡眠時間の増減はないか
- 生活リズムは規則正しいか
- 運動習慣は適切か
- 食事量・回数は適切か
【就労状況】
長時間労働などの就労状況について従業員に聞き取りをおこないます。長時間労働は疲労が蓄積するため、心臓や脳に影響を及ぼす危険性が高いです。
産業医は対象者の健康状態を把握し、健康障害の発症を予防するためのアドバイスをおこないます。
面談後、産業医は就業判定や必要な措置に関する意見書を作成し、企業は産業医の意見を踏まえ、就業状況改善をおこないます。
*質問例
「体や心の調子はいかがですか?」
「復職するにあたり、不安なことはありませんか?」
従業員はどのように回答すればよい?
産業医面談では、従業員は自身の現状を正直に伝えることが大切です。体調、生活習慣、仕事の状況などについて、できるだけ具体的に説明するのが重要です。
もし何か気になる点や改善したい点があれば、積極的に相談することで、より適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
企業が産業医面談で配慮すべき4つのポイント
企業が産業医面談を実施する際には、従業員のプライバシーを守り、面談の重要性を理解してもらうことが大切です。ここでは、企業が産業医面談で配慮すべき4つのポイントを紹介します。
①面談対象者への案内はプライバシーに配慮する
産業医面談の対象者へ面談の案内をする際には、プライバシーに配慮しましょう。産業医面談は、メンタルヘルス不調者や高ストレス者など、従業員が周囲に知られたくない内容が含まれています。
産業医面談の対象者に通知する際は、封書やメールを活用したり、個人面談を設けたりするなど、プライバシーに配慮した方法を取りましょう。
②産業医面談の重要性を従業員に周知する
産業医面談の目的や役割を従業員に説明し、従業員が心身共に健康的に働くために大切な取り組みである旨を伝えましょう。
従業員の中には、企業に面談の内容が知られたり、人事評価で不当な扱いを受けたりする旨を懸念し、面談に抵抗を感じる人もいます。
産業医は企業と従業員に対して中立の立場にあります。守秘義務があるため、本人が同意しない限り面談内容は企業側へ共有されない旨や、人事評価で不利益を被ることはない旨を伝え、安心して面談に臨めるようにしましょう。
③面談結果を踏まえて業務内容や労働時間を見直す
産業医の意見書を元に労働時間の見直しや、業務量・業務内容の見直しを検討し、従業員が心身共に良好に働けるようにします。
過重労働の場合は、衛生委員会などで内容の調査や審議が必要なケースもあります。
④産業医と協力して従業員の健康管理をサポートする体制を整える
企業は、産業医と連携して従業員の心と身体の健康を守り、よりよい職場環境を作れるようにサポートします。
企業と産業医が連携する際に、お互いの方向性が違っていると適切なサポートができない出てくる可能性がありますので、同じ意識を持って取り組めるようにしましょう。
Dr.健康経営では、連携がとりやすいプロ産業医のご紹介をしております。ややこしい産業保健体制の立ち上げサポートも手厚くしておりますので、導入の検討時は参考にしてみてください。
産業医面談を拒否されてしまった場合はどうする?
産業医面談は、従業員の健康管理をサポートするために実施されますが、時には従業員が面談を拒否することもあります。面談を拒否された場合、企業はどのように対処すべきかについて解説します。
従業員は産業医面談を拒否することが可能
産業医面談は、労働安全衛生法に基づく企業の義務があるが、従業員には面談を受ける法的義務はありません。そのため、従業員が面談を拒否することも可能です。
産業医面談を拒否された場合の対処法とは
拒否された場合、企業はその理由を確認し、面談の目的を改めて説明することが求められます。場合によっては、他の手段を検討し、従業員の健康管理に取り組む必要があります。
産業医面談の実施で心身ともに健康な企業を目指そう!
産業医面談は、企業と従業員双方にとって多くのメリットがあります。適切に実施し、従業員の健康を守ることで、職場全体の生産性向上にもつながります。企業は産業医と連携し、健康経営の一環として積極的に活用することが求められます。事業所ごとに適切な対応を講じましょう。
以下の資料は、電子申請義務化の背景と、企業が取るべき具体的な対応策をまとめた資料です。
ぜひ業務にお役立てください。
>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :電子申請義務化の背景と対応策を解説
mediment(メディメント)であれば、健康診断、ストレスチェックに関する業務やオンライン面談、産業医との連携も一元管理でスムーズにおこなえますので、お問い合わせください。
>>>「mediment(メディメント)」の資料ダウンロード(無料)はこちらから