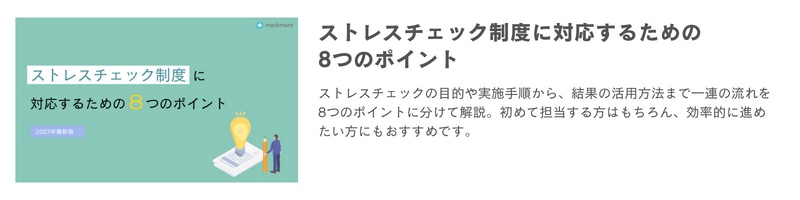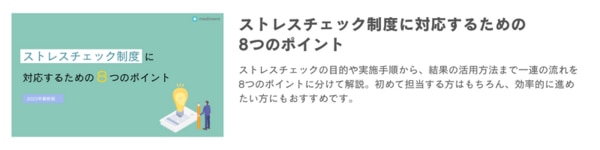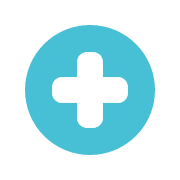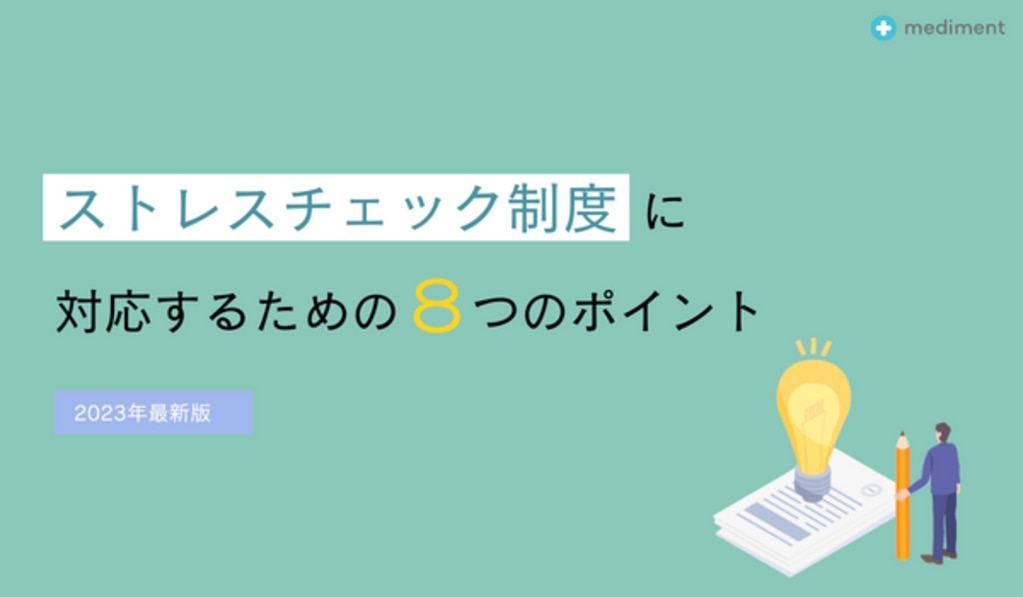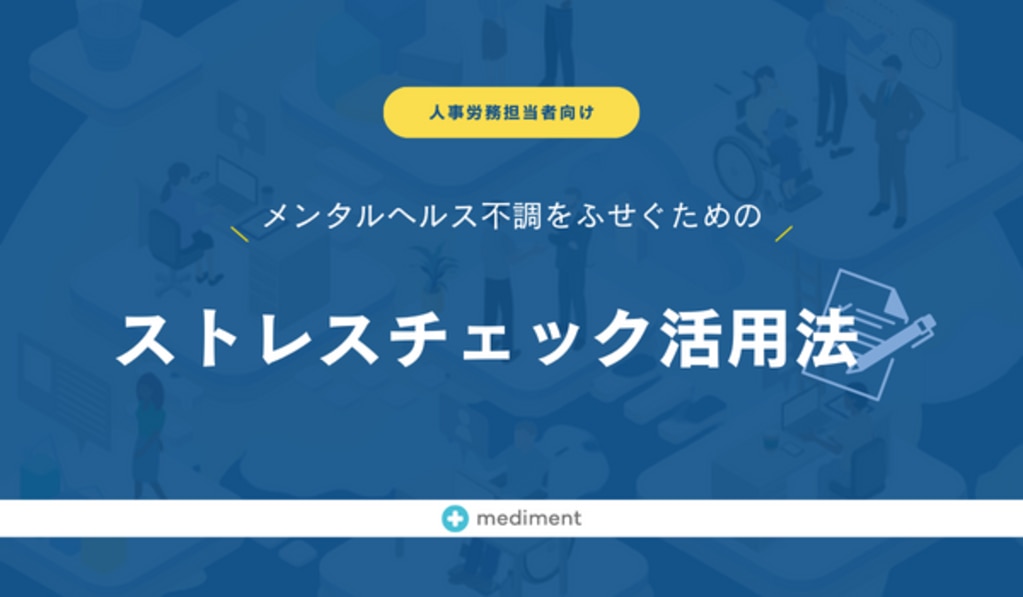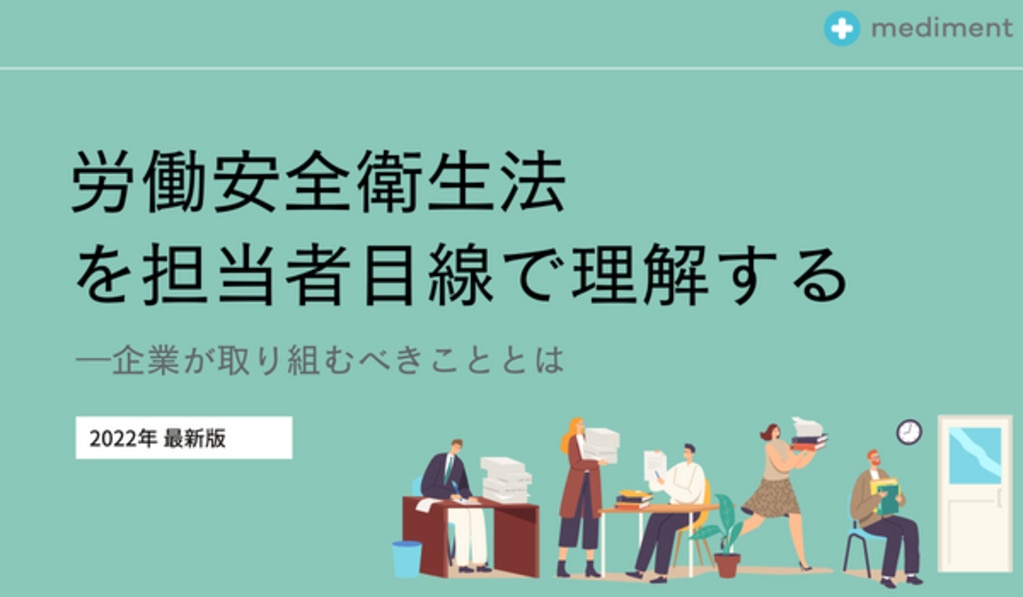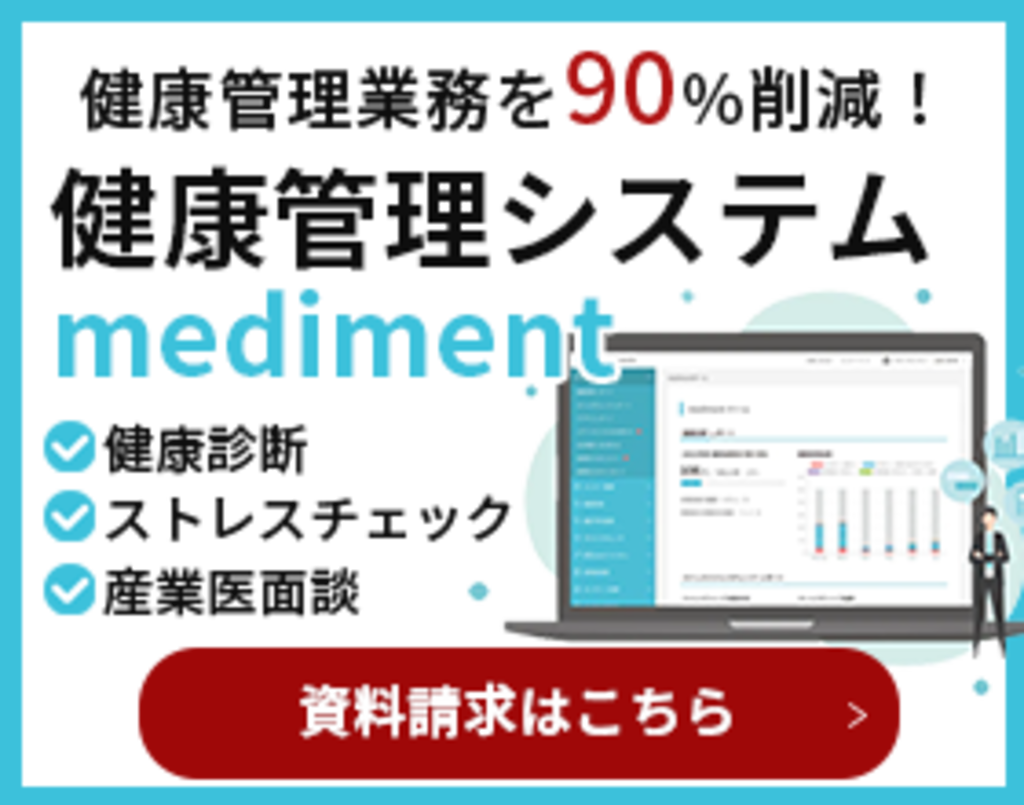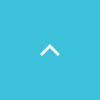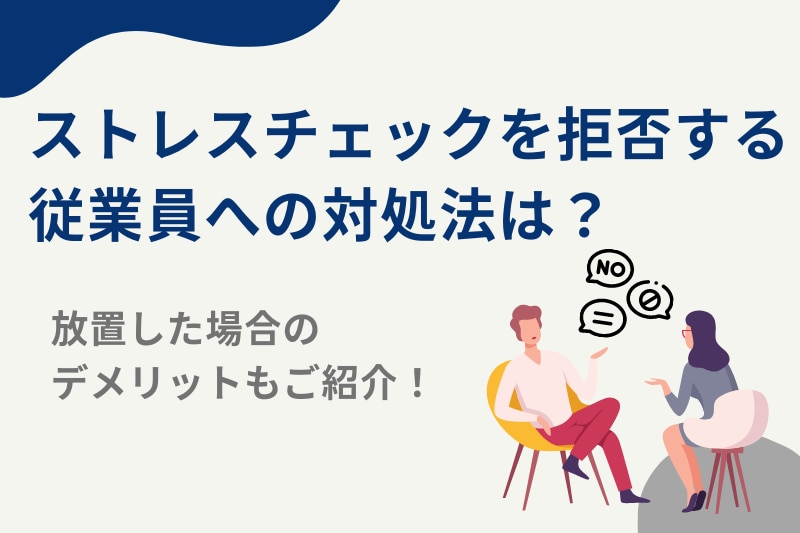
ストレスチェックは企業の義務?拒否された場合の影響と取るべき対応
資料ダウンロード「ストレスチェック制度に対応するための8つのポイント」
「ストレスチェック」という言葉は、企業に勤めている人ならば、一度は耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
しかし、昨今では「ストレスチェック」を受けたくないと拒否する従業員が増え、企業側の人事部や労働管理担当者から悩みの声が募っています。
本記事ではそんな企業側の悩みを解決するべく、ストレスチェックを拒否する従業員への対処法や放置することによる、企業側・従業員側のデメリットそれぞれを解説します。
目次[非表示]
ストレスチェック制度とは?企業が知るべき概要
ストレスチェック制度とは、従業員のメンタルヘルス不調を予防するための制度です。一定規模以上の企業は、年1回のストレスチェック実施が義務化されています。
この見出しでは、ストレスチェック制度の概要や対象者、企業が取り組むべきメリットをご紹介します。
ストレスチェック制度とは
2015年12月から施行されたストレスチェック制度。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした、企業にとって重要な義務です。
一定規模以上の職場では、年に1回、労働者を対象にストレスチェックを実施し、労働基準監督署への結果報告が義務化されています。主な取り組みは、ストレスチェック検査の実施、面接指導、集団分析などです。
ストレスチェックの実施者と対象になる従業員
ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者は、産業医や医師、保健師、そして研修を受けた看護師や精神保健福祉士など、専門的な知識を持つ人が担当します。
また、実施をサポートする実施事務従事者は、診断結果の守秘義務があるため、総務担当者などの人事権を持たない従業員が務めます。
ストレスチェックの対象となる従業員
ストレスチェックの対象者は、以下のいずれの要件も満たす者です。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること
- 週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
契約期間が1年以上(1年以上契約される見込みのある者を含む)あるいは1年以上働いており、所定労働時間が4分の3以上となる者であれば、契約社員やアルバイト、パートであってもストレスチェックの受検対象者となります。
また、派遣社員は派遣元の事業者にストレスチェックの実施義務があります。
ストレスチェックを実施する企業にとってのメリット
ストレスチェック制度を導入することで、企業は様々なメリットを享受できます。
まず、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を取ることで、症状の悪化を防止できることが挙げられます。
また、ストレスチェックの結果を分析することで、職場環境における問題点を把握し、改善につなげることが可能になります。
その結果、従業員のストレス軽減、モチベーション向上、労働生産性の向上などが期待できます。
さらに、従業員のメンタルヘルスが改善されれば、退職や休職のリスクを減らし、採用や教育にかかるコストを抑えられる可能性も高まります。
ストレスチェックの実施状況と企業の義務について
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見が目的ですが、実際にはどの程度の企業がストレスチェックを実施しているのでしょうか。
また、企業にはどのような義務があるのでしょう。この見出しでは、ストレスチェックの実施状況と企業の義務について詳しく解説します。
ストレスチェックの実施状況
ストレスチェックの実施状況について、2022年時点での実施率は84.7%でした。
一方で、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%という結果が出ています(厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」2017年7月26日)
ストレスチェックにより、労働者のメンタルヘルス不調を早期発見し、未然に防ぐくことができれば、事業所にとって労働生産性アップにつながります。労働者のストレスチェック受検率が低い現状は、事業所にとって悩ましい問題といえるでしょう。
【参考】 「職場におけるメンタルヘルス対策の現状等」 (厚生労働省)
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001236814.pdf
ストレスチェックの実施義務
2015年12月から年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。事業場の法人格の有無に関わらず適用されますが、法的な罰則はありません。
労働者が常時50人未満の場合
現時点では、ストレスチェックの実施は努力義務となっています。しかし、2024年10月に厚生労働省は、全ての企業に対してストレスチェックの実施を義務付ける方針を発表しました。
従業員が50人未満の企業は97%、従業員数は全体の60%を占めると言われています。実施時期は未定ですが、今後の動向に注目が集まります。
従業員はストレスチェックを受ける義務がある?
ストレスチェックの実施は、2015年12月から開始され、常時使用する労働者の人数が50人を超える場合は、実施義務があります。
事業者はストレスチェックを実施しなかったからといって法的な罰則があるわけではありませんが、労働者の人数に応じてストレスチェックをする必要があります。
一方、労働者がストレスチェックを受けるか否かは本人の自由となっています。
ストレスチェックの拒否が与える影響と企業の取るべき対応
ストレスチェックの受検は強制ではありませんが、拒否をすることによって様々な影響があります。
従業員と企業、それぞれへの影響と拒否された場合に企業がとるべき対応についてご紹介します。
ストレスチェックの拒否が与える影響
従業員側のデメリット
ストレスチェックを拒否することで、自身のメンタルの状況を把握しにくくなり、セルフケアがおろそかになる可能性があります。
ストレスチェックは、労働者それぞれが自己では気づけない「心の変化」や病気になる前の「疲れ」に気づけるチャンスの1つです。心の不調に気づけなければ、最悪の場合、自殺や過労死などを引き起こしかねません。
しかし、早期に心の不調や病気に気づければ、心の病気や体調不良を回避できるだけでなく、仕事へのモチベーションアップにつなげられるでしょう。
企業側のデメリット
ストレスチェックを拒否する労働者が増えることで、企業側にとって2つの問題があります。
1つ目に、メンタルヘルス不調に陥る労働者の早期発見に遅れ、休職・退職者が増加するリスクが高まります。貴重な労働力が失われ、生産性も下がってしまいます。
2つ目に、ストレスチェックを拒否して受験しない従業員が、メンタルヘルス不調を起こし労災に発展した場合には、労働基準監督署から「安全配慮義務違反」としてストレスチェックの受検勧奨を怠っていたという指摘が入る可能性はあるかもしれません。
つまり、労働者のメンタルヘルスに関する健康リスクに目を向けていないと見なされてしまうということです。ストレスチェックの受検はあくまで労働者の自由ですが、企業の信用につながるため、企業側にとって、労働者のストレスチェック拒否は解決したい問題といえます。
企業が知っておきたい「安全義務違反」とは
企業者にとって、ストレスチェック実施をするにあたり、知っておくべき、「安全配慮義務違反」があります。
「安全配慮義務」とは、企業側が労働者に対して安全に働くことができるよう準備や配慮をする義務をいい、「安全配慮義務違反」は、ストレスチェック制度において企業側が労働者の受検拒否への受験勧奨などの、適切な対応をしなかったことで違反とみなされることをいいます。
従業員にストレスチェックを拒否された場合に取るべき対応
ストレスチェックを拒否する労働者に対して、企業が行うべき適切な対処法はどのようなものか、詳しく見ていきましょう。
1.拒否の理由をヒアリングする
まず、従業員がストレスチェックを拒否する理由を知ることが大切です。例えば、人に言いづらいことや心配事があるなど、従業員が拒否するのには心理的なストレス要因や不安等の理由が隠れている可能性が高いです。
従業員のプライバシーに配慮しながら、拒否する理由をヒアリングして、従業員への理解を深めることが必要です。そして、対策を行っていくことで、ストレスチェックに対する受検の心理的抵抗を無くせるでしょう。
2.制度の目的を明確にしてメリットを伝える
ストレスチェックを拒否する理由として、ストレスチェックに対する心理的抵抗や不安により、ストレスチェック制度に関する理解がされていないことが挙げられます。
従業員へストレスチェックに関する理解を深めるための取り組みとして、ストレスチェック制度そのものや制度の目的、メリット・デメリットを説明する等、企業側の努力も大切です。
従業員へのメリットとしては、ストレスチェックで早期に心の不調に気づくことができれば、早い段階で対処ができるのでメンタルヘルス不調や休職などのリスクを回避できる点が挙げられます。
3.高ストレス者には医師の面接指導を勧奨する
ストレスチェックを受け、「高ストレス者」と判定された場合、企業は受検者である労働者へ、医師による面接指導を受けるよう勧奨を実施します。
高ストレス者、つまりストレスの程度が高いと判定された労働者は、目に見えない部分でストレスを抱え、うつ病などの精神疾患の一歩手前であるケースもあります。
面接指導は、高ストレス者が自己のメンタルを正しく認識し直せる機会提供につながるため、企業は高ストレス者への面接指導等の勧奨を積極的に実施することが大切です。
ストレスチェックは企業で取り組むべき仕組み!拒否されても適切なフォロー&体制づくりを
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を早期発見し、企業と従業員双方にとって不利益となる事態を防ぐための重要な取り組みです。企業の義務として、適切な実施と結果の活用が求められます。
従業員がストレスチェックを拒否した場合でも、企業は対話を重ね、制度への理解を深める努力を怠らないことが大切です。ストレスチェック制度を積極的に活用し、従業員の健康を守り、健全な職場環境を実現しましょう。
資料ダウンロード「ストレスチェック制度に対応するための8つのポイント」