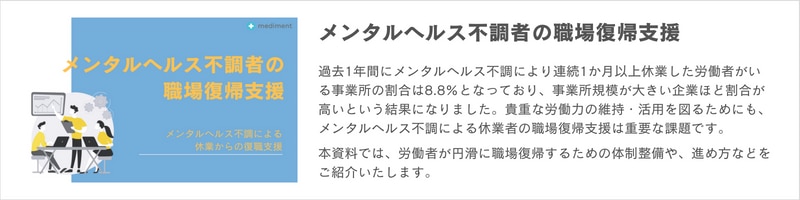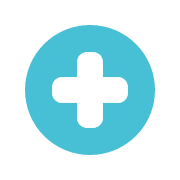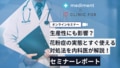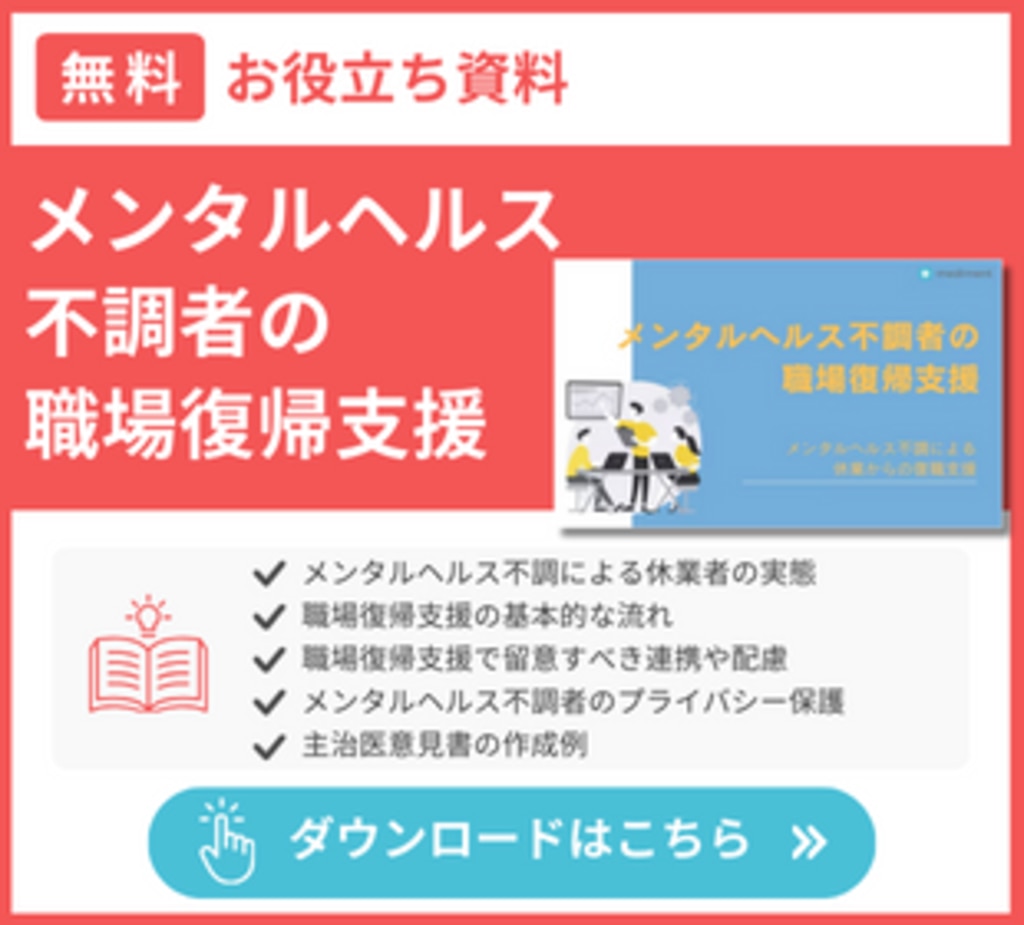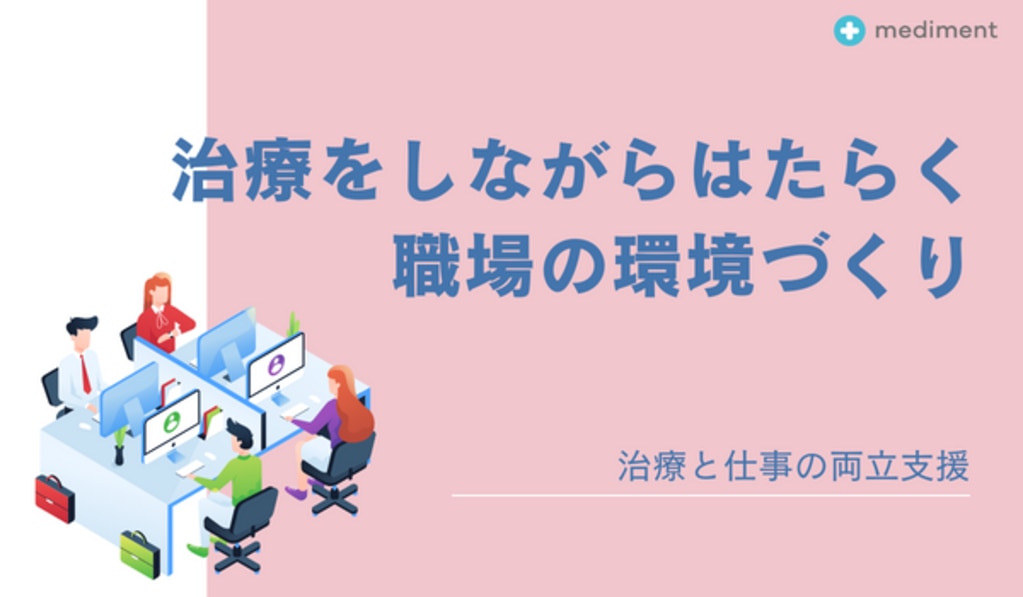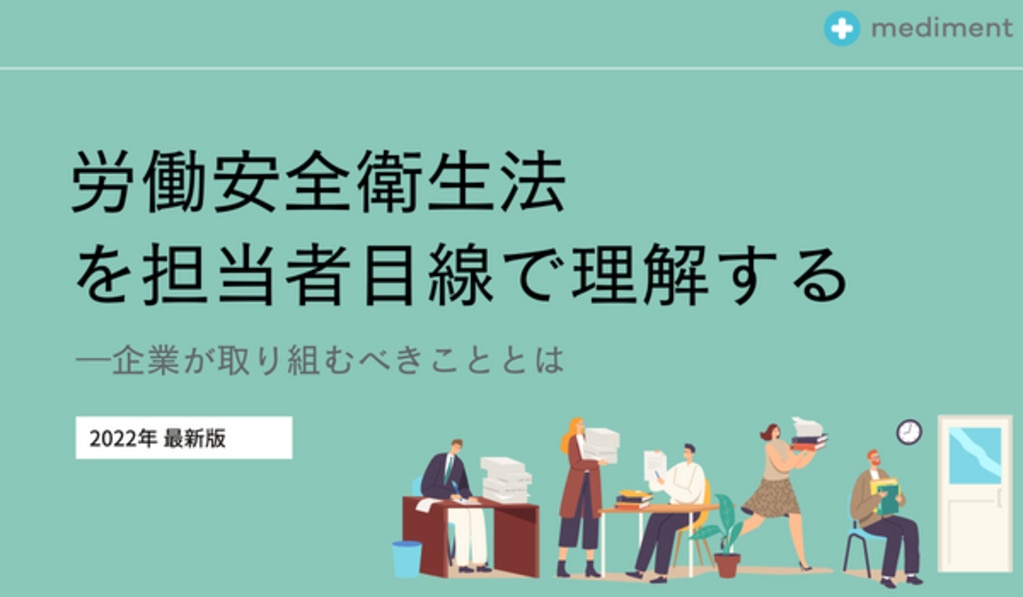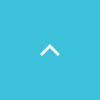適応障害の従業員に対して職場や会社ができるサポートや備えとは
仕事や職場環境がストレス要因となり、適応障害と診断される人が増えています。強い不安や心身の不調が起き、職場に行くことが困難となって休職または退職に至るケースも少なくありません。
今回は、従業員が適応障害と診断された、または従業員から適応障害を原因とする休職の申請があった場合に、会社や職場ができるサポートや備えについてご紹介します。
目次[非表示]
メンタルヘルス不調者の復職支援については、こちらのお役立ち資料で詳しく解説しています。
>>>資料ダウンロード(無料):メンタルヘルス不調者の職場復帰支援
適応障害の特徴
よく耳にする適応障害とはどのようなものなのか、その特徴についてご紹介します。
適応障害の症状
適応障害とは名前のとおり、自分のいる環境への適応がうまくいかず、何らかのストレスにより心身のバランスが崩れて、日常生活に支障をきたしている状態です。
ストレスの原因が明確で、それに対する反応が起こった状態のことを指します。
その症状には個人差がありますが、主に抑うつ気分、不安、不眠、頭痛など、対人関係や社会生活を続けることに支障が出る状態になることが多くあります。
また、無断欠勤や無謀な運転、喧嘩、物を壊すなどの行動面の症状もみられます。これらの症状は、ストレスになる出来事が生じた際に現れ、ストレス因子がなくなった後6ヶ月を超えて続くことはありません。
ストレス因子の出来事が生じて1ヶ月以内に症状が現れ、6ヶ月以上続く場合、症状が悪化する場合には他の病気の可能性も考えられます。ただ、ストレスが慢性的に存在する場合には、症状も慢性に経過します。
適応障害が起こりやすい環境・状況
一般的に、日常生活のなかで起こった出来事に対して、上手く対処できずにいると落ち込んだり、悲しくなったり、怒ったりするといった反応をとることは少なくありません。
しかし、同じような体験をしても適応障害の症状が現れる人とそうではない人がいます。これは人格・精神の弱さではなく、主観的な体験の違いによるもので、適応障害の診断にとっても重要な認識とされています。
適応障害の場合はそれを超えた過敏な状態であり、日常生活に支障が出ていることが特徴です。適応障害が起こりやすい環境や状況には、個人レベルから災害など地域社会を巻き込むようなさまざまなレベルまであります。
例えば新しい職場での勤務、プロジェクトの責任者就任や昇格による新たな役割、長時間労働や休日出勤などの超過労働、人間関係やハラスメント、失業、金銭的トラブル、恋愛的挫折、離婚、持続的問題(障害のある家族の介護など)、身近な人の死などがあげられます。
適応障害を引き起こす原因は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)のようにトラウマになる出来事ばかりではありません。しかし、原因となったストレスが明確であることが特徴です。
実際には、新規事業の担当となったことをきっかけに適応障害を発症したとして労災認定された事例もあります。
適応障害の診断、似ている病気
適応障害は、ストレス因子に対する反応であること、そのストレス因子が始まってから1ヶ月以内に発症し、ストレス因子がなくなれば6ヶ月以内に軽快すること、その症状の程度や強度は通常考えられるものよりも著しい苦痛をもたらしていることとされています。
ただし、正常な死別反応のように、適応障害と診断するにはグレーゾーンが存在すると考えられています。「他の精神疾患の基準を満たしていない」という要件で、適応障害との鑑別で最も重要なのは、うつ病です。
適応障害はストレス因子と症状の発現・消失の時間によって診断される一方で、うつ病は症状の数と持続期間によって考えられます。そのため発症時点では確定されず、症状や持続時間が増してうつ病の診断が濃厚になるケースもあります。両者の鑑別は簡単ではありません。
うつ病の可能性がある人の仕事における特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。
従業員が適応障害で休職した後、会社や職場でできるサポート
適応障害で従業員が休職した後に、会社や職場でどのようなサポートができるのか、まとめました。
適応障害で休職するときの流れ
適応障害に限らずうつ病などを含む心の健康問題による診断で休職となった場合、以下のような流れで進んでいきます。
-
診断で病気休業開始、休業中のケア
- 従業員からの診断書の提出
- 管理監督者や事業場ない産業保健スタッフによるケア
- 求職中の復帰に向けた訓練・目標
↓
-
主治医による職場復帰の可能性の判断
- 社員からの職場復帰の意思表示、職場復帰可能の診断書の提出
↓
- 社員からの職場復帰の意思表示、職場復帰可能の診断書の提出
-
職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成
- 情報の収集と評価(職場復帰の意思の確認、主治医からの意見、従業員の状態、職場環境の評価など)
- 職場復帰の可否についての判断
- 職場復帰支援プランの作成
- 試し出勤などの検討(職場復帰日、主治医や産業医の意見、就業上の配慮、人事労務管理上の対応、フォローアップ)
↓
-
最終的な職場復帰の決定
-
従業員の状態の最終確認、主治医の意見や本人の希望、職場環境をもとに、就業上の配慮を決定。職場復帰後の就業上の配慮を主治医へ連絡
↓
-
従業員の状態の最終確認、主治医の意見や本人の希望、職場環境をもとに、就業上の配慮を決定。職場復帰後の就業上の配慮を主治医へ連絡
-
職場復帰
↓ -
職場復帰後のフォローアップ
- 症状の再燃・再発、新しい問題の発生有無の確認、勤務状況、業務遂行能力の評価、職場復帰支援プランの評価と見直し
職場復帰については厚生労働省より、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が作成されており、事業所や衛生委員会などにおいて職場の復職支援に関する体制を整備、ルール化して進めていく必要があります。
事業所においては、上記の休職から復職までの流れをあらかじめ明確にすることが大切です。
人事労務担当者としては、人事労務管理上の問題点の把握をし、労働条件の改善、配置転換・異動等の配慮をおこなう役割があります。
また、管理監督者は現場環境の問題点の把握と改善、就業上の配慮、職場復帰後の労働者の状態観察などをおこないます。
産業医は専門的な立場から管理監督者および人事労務管理スタッフへの助言および指導、主治医との連携における中心的役割、就業上の配慮に関する事業者への意見などをおこないます。
保健師は労働者に対するケア及び管理監督者に対する支援をおこないます。
適応障害がある従業員に対して会社や職場ができるサポート
こうしたメンタルヘルス対策については労働安全衛生法第70条の2に基づき、事業者が努めるべき措置として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が厚生労働大臣によって定められています。
特徴的なのは、以下の4つです。
-
セルフケア
- 事業場において労働者自らのケア、事業者はこれを支援すること
-
ラインによるケア
- 管理監督者によるケアで部下の健康管理や職場環境の改善など
-
産業保健スタッフによるケア
- 産業医や人事労務管理担当者などによるケア
-
事業場外資源によるケア
- 公的な機関のおこなう研修やコンサルティング事業などの活用、精神科医やEAPを活用した専門的なケアなど
適応障害においては、ストレス因子が明確であることが多いため、特にそのストレス因子について関係者と相談することが大切です。これらが継続的かつ計画的におこなわれるよう教育研修や情報提供をおこなっていきましょう。
産業医等がいない事業場の場合、たとえば職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成にあたっては、本人の同意を得た上で、本人、主治医、人事労務担当者あるいはライン管理者、もしくはその両者による面談をおこなうことがあります。
また、メンタルヘルス対策を進めるにあたって、心の健康問題の特性や労働者の個人情報の保護への配慮、人事労務管理との関係、家庭や個人生活の職場以外の問題に気を付けることも大切です。
4つのケアについてはこちらで詳しく解説しています。
適応障害の再発に対する備え
仕事復帰時は本人の健康状態は必ずしも完全な状態とはいえない場合もあります。症状によっては注意力や集中力の低下や疲れやすさが残ることもあり、仕事の内容や量は本人の希望や主治医の意見を聞きながら決めることが大切です。本人は休職したことによって、迷惑をかけた分を取り戻そうと焦り、無理してしまうこともあるため、無理させないように見守ることも必要です。
特に上長は本人の業務範囲や配慮の期間を明確にし、業務の流れをコントロールする役割があります。職場の他のメンバーにも復職後の業務や配慮の期間など計画を説明しておくことも必要です。
また、職場におけるメンタルヘルス活動には、できること・できないことがあります。職場は病院やリハビリテーション施設ではないため、適応障害に対する限界や危険性を認識する必要があります。そのため、産業医が常勤でいない職場が多いなかで、産業保健スタッフや人事労務担当者などが外部の専門機関や他職種に紹介、援助を依頼することもあります。
依頼先としては一般的な精神科医療機関をはじめ、産業保健推進センター、地域産業保健センター、精神保健福祉センター、保健所、労災病院、勤労者メンタルヘルスセンターなどがあります。
EAP(従業員支援プログラム)を活用しているところも増えてきています。こうした外部の資源をうまく活用し、他職種と連携していきましょう。
適応障害に対して会社や職場としてどう対応するべきかを知ろう
従業員が適応障害と診断されたとき、また休職・復職の際には事業者の適切な対応が求められます。人事労務担当者として適切なサポートができるように、また再発の備えについても理解し、日頃から取り組んでいきましょう。
メンタルヘルス不調者の復職支援については、こちらのお役立ち資料で詳しく解説しています。